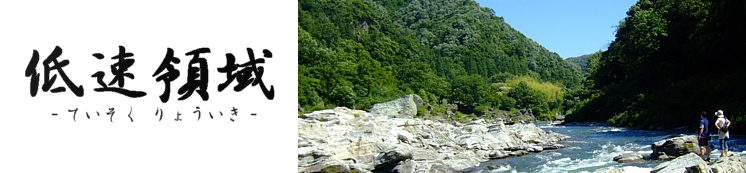| -低速 領域-
救いの死神 ―私は、空を飛ぶのが夢だ。 大空を自分の力で飛び回りたい―・・きっと誰もが幼い頃に抱いた夢。 だけども私はもう高校生になるが、その夢を一度も諦めた事は無く、未だに幼い子供のように憧れていた。 友人達はそんな私を「ロマンチスト」とか「夢見がち」等とありふれた妄言を含めて呼んでいる。それは私に対する侮辱も少なからず入っていたが、私は何一つ文句も言わず、黙っていた。 何故なら私は悪口やらを言われても怯まない性格であったし、何より私は、自分の事を誰よりも奇人だと認めていたから。 1. ―酷い倦怠感だ 朝が来るたびにそう思う。 この朝起きたときの何ともいえない不快感、そうこれからまた一日が始まるという気だるい感覚・・・私は朝が大嫌いだった。 いつ頃からそうなったかは覚えていないが、確かかなり昔からだった気がする。学校がある平日は勿論そうだが、夏休みや冬休み、普段なら楽しいはずの休みの朝も私にとっては凄まじい苦痛でしかなかった。 だが昼や夜が楽しいというわけでは無く、端的に言ってしまっては、私にとっては生きること全てが苦痛だったのかも知れない。 ―でも、そんな私が今まで生きてきているのは、あの幼い頃から描いてきたあの夢があったからかだと、私は確信している。 2. 私はまた学校をサボった。 2学期が始まってから一度も学校に通った事は無かった。それは決して誇れる行為では無かったが、私は学校をサボった事に対して妙な優越感、というか自由を手に入れた開放感があった。 そんな事を考えるのは余程腐っている人間だろうが、今の私は自分が腐っていようが全くと言って良いほど関心が無かったし、そんな事を気にする程繊細な考えが出来る人間ではなかった。 そしてまた、当ての無い私は気づくとここにいた。それは、町外れにある廃ビルの屋上。 バブルの頃の遺産らしく、建物は堅牢で放置されても崩れる事は無さそうだった。最も、入り口にはご丁寧に「立ち入り禁止」の看板が置いてあるのでその事を知るのは私だけだとは思うが。それでも時折、工事関係の人らしき人が来て色々検査しているようで、私はその度にこそこそと避けるように隠れていた。 この廃ビルはそこそこの高さで、屋上から落下したら普通に逝ってしまいそうな高さだった。大体8階程度のビルで、屋上から下を見下ろすとゴオゴオと風の音がした。 (・・死ぬときは此処から飛び降りて死ぬのもまた良いかなぁ) 私はそんな不謹慎な事を考える。今すぐ飛び降りれそうな気がしたが、それは何となく、気が向かないので止めておいた。だが、近いうちに此処から飛び降りそうな気がしたのでもう一度屋上から下を覗いて「死に場所の下見」をした。自分が奇人だと言うことを改めて認識した気がする。 この廃ビルは、私のお気に入りのスポットだった。不気味なまでの静寂が私には心地よかったのかもしれない。 私は、外の自動販売機で買ってきた暖かい缶コーヒーを飲みながら、何をするでも無くゆっくりと過ごしていた。私は毎日、この状態でたいがいを過ごす。 周りから見れば、私の行為は酷く退屈で理解し難いだろうが、私にとってこの行為は、楽しくはないが非常に楽な事だった。 時折空を飛ぶ鳥達を眺める私は、幼い頃から思い描いて来た自分の夢に、思いを馳せる。 果てしない蒼穹を自由に飛び回る鳥達。私はその鳥達を羨ましそうに見ていた。 でも、私は最近改めて思う。なんで、こんなに幼い夢を信じているのだろうかと。 正直言って、こんな年齢でこんな幼い夢を信じるなんて、ちょっと異常だと思っている。でも、私はこんな幼稚な夢を信じる事によって、なんとなく自分を保っているようだと実感していた気がした。 3. タータータータン ターターターターターター・・・ 近所の公園でなるチャイム。 ふと私が気づくと、空は茜色に染まっていた。 またここで一日を過ごしていたようだ。時が経つのは早い、と私は思い名残惜しそうにその場を立ち去った。 ―この帰り道も、私は嫌いだ。 まるで、楽しい事が終わった後のような切なさ・・・尤も、私が今まで楽しいと感じた出来事は何一つ無いような気もするが・・兎に角、憂鬱なのだ。 家へ帰れば学校をサボったと五月蝿いし、家にいても何もする事は無い。 家出をしても良いが、それでは後々面倒な事になるので止めておいた。 一時間くらい歩いただろうか。 既に空は茜色から、濃紺色へと変わってきていた。一日の終わりを象徴するようなその色は、どこと無く寂しい。 ようやく家の前に着くと、私は少し躊躇った後、仕方なく家に入っていった。 「ただいま」 私が小さく言う。 だが、直感的に家には誰もいない事は分っていた。私の両親は二人とも不倫をしていて、お互い家にいない事が多い事を私は前から知っていたからだ。 なんて冷たい家庭なのだろう、とは思わなかった。なにせ私の家族は、昔から私に冷たかったし、両親の暖かさというものを何一つ知らなかったから。 家は、相変わらずの静寂だった。 私は居間へ行きテレビの電源を入れる。だが、テレビを見るつもりは全く無く、ただ何となく理由も無く付けただけだった。 テレビをBGM代わりにして私はくだらない考え事をしていた。それが何の考え事だったかは覚えていない。恐らく、忘れてしまうほどくだらない考え事だったのだろう。 あれから私は風呂に入った後に夕食を取った。夕食は冷蔵庫に入っていたお弁当で済ました。冷蔵庫に材料はなかったし、何より自分で料理を作る事はこの上なく面倒な事だというのが私の考え方であったから。 私は味気ないコンビニ弁当を頬張りながら、これまた味気ない声で話すニュース番組を長々と見ていた。それでも一行に両親は帰ってこなかった。 ニュース番組が終わると、もう時計は11時を指していた。時間とは泡沫なモノだな、あっという間に過ぎて、もう2度と戻って来ないんだから。この先も、このつまらない、泡沫な時間がただただ流れていくだけ。私は、この先、生きていくのが余計面倒になってしまった。そして、私は心の中できっぱりと、決心した。 ―明日、死んじゃおう。と 4. 翌日の朝は、何故か何時ものような倦怠感が無かった。 私にしては珍しく、朝の7時にはしっかりと起きていたのだった。学校には行かないのに、制服に着替えた私は居間へ続く階段を、トン、トンと軽快に、調子よく降りた。今日は何時に無く、気分が爽やかだ。昨夜、やっと自分の人生に見切りをつけられたからだろうか。 私が居間に行くと、母親がソファに座って朝のワイドショーを見ていた。やがて、私が居るのに気づくと「あら、いたの」と一瞥してまた目をテレビに目を向けた。 テーブルの上には母が食べた弁当のゴミが散乱している。当然ながら、私の分は用意されていない。だが、悲しくは無かった。 「―あんた、また学校サボったんだって?」 立ち尽くしている私に母は言った。それは馬鹿にしたような、私にとってとても不快な声だった。 母は、私に顔を向け更に続ける。 「なんで、あんた見たいな出来損ないが出来てきちゃったのかしら」 クスッ、と母は嘲笑を含めて言った。 ―・・あなた達両親が愛情を注いでくれなかったから、あなた達両親が私を歪んだ人間に育てたから、あなた達両親が―・・全部、あなた達の所為。 私は、そんな事を考えていた。だけど、その事は決して口には出さなかった。 母は、全く動じない私を見て、つまらなさそうに「フン」と鼻を鳴らしてまたテレビへ目を向ける。 ―そうだ 私は、ふと思いついた。 ―お母さんにも、少し仕返しをしてあげよう。今まで散々言われて来たんだもの。 そう思った私は、冷蔵庫を開け、賞味期限をとっくに過ぎた「生卵」を手に取った。 そうして、母と直線上に立って、いつも通りの抑揚の無い声で言った。 「お母さん」 「何よ!?」 振り向いた母に向かって、私は手にしていた生卵を思いっきり投げた。 ―ベシャ 見事顔面に直撃して、母は「きゃぁ!?」と素っ頓狂な声を上げた。私はその姿を見て、急いで家から飛び出した。後ろから母の怒鳴り声が聞こえた気がしたが、私は初めての母親への反抗に気分が高揚していたようで、無視して廃ビルへ向かって全速力で走り出していた。 5. 久しぶりの運動にすっかり息の上がった私は、ようやく廃ビルの前にたどり着いていた。やがて、体力も回復し落ち着いた私は廃ビルの中へゆっくりと入っていった。 ―死を決意した私を、廃ビルは相変わらずの静寂で私を迎えてくれた。 ひんやりとした空気と、時間が止まったかのような凪。そして、来る者を抱擁するような静寂。全てが、普段通りのはずだった。 だが、その時私は何か違和感を感じた。どちらかと言うと鈍い私だが、この感覚ははっきりと分かる気がした。 「・・屋上だ」 そう直感した私は、屋上への階段を登り始めた。怖くは無かった。何故なら私の感情に「畏怖」という感情は存在しなかったから。 バン!と勢い良く私はドアを開けた。その拍子に蝶番が壊れそうになったが、私はそんな事は気にしないで屋上を見渡した。だが、そこには人っ子一人居なかった。 「気のせいか・・・」私は一人で呟く。予想はしていたが、なんだか変な喪失感が私の心を満たす。そう、それは願いが叶わなかったような喪失感にとても似ていた。 「―こんにちは、お譲ちゃん」 不意に、老人の声が後ろからした。私は即座に振り向かかず、その場で気が抜けたような深呼吸をしてゆっくりと、振り返る。 振り返った私の眼前には、背筋のピンとした男性老人が立っていた。古ぼけたタキシードと、シルクハットを被っていて、私は昔の紳士を連想した。手には木製の杖を持っていて、時折クルクルと軽快に回している。 「こんにちは」 私はきっぱりと言った。私のその言葉に、老人は柔和な表情を浮かべて優しく笑う。老人は笑いを浮かべたまま私に歩み寄りながら言った。 「お譲ちゃんには、夢はあるかい?」 優しく、限りない慈愛に溢れた声だった。私はその質問に、強く頷いた。 その私の反応を見た老人は、優しい瞳を私に向けゆっくりと言う。 「・・なら、その夢を叶えてあげよう。言ってごらん」 ―なんなんだ、この人は、と私は思った。だが老人の澄んだ瞳を見ると、奇妙なことに私の老人に対する不安や疑いは薄れていった。もしかしたら、私の人生の中で一番信頼できる人かもしれない、とまで思いはじめたのだ。 「言ってごらん。言いづらい夢でも、ワシは真摯に受け止めよう」 先程より真剣な口調で老人は言う。私は、この老人に夢を、幼くて言い辛い夢を言う事にした。私がここまで自分の夢に恥じらいを覚えた事は後にも先にも始めてだろう。 「・・―空、飛ぶ事、です」 驚いたことに、自分の声はたどたどしく、震えていた。老人は私の答えに、少しだけ意外そうな顔をして、すぐまた優しい表情に戻った。 私は、老人の反応を待っていた。何故だか足が震える。私は自分の行動を心の中で嘲笑した。 老人は相変わらず杖をクルクルと回していた。何を考えているのだろう、と私が思っていると、不意に口を開く。 「君は、珍しく純粋な子じゃな。それでも、君は死を望むのかい?」 意味がわからなかった。純粋?死?望む?一瞬で私の頭は訳がわからなくなった。やがて、私の状態に気づいた老人は「ああ」と、納得したように呟く。そして、またにっこりと微笑み言う。 「そうか、まだお譲ちゃんには言って無かったか。私は、「救いの死神」と言う者。人が死を望んだときに現われる神様じゃな。私の仕事は、『命を奪う引き換えに、夢を叶える』と言うものじゃよ。」 淀みの無い老人の声で紡がれる言葉は、全てが真実のように聞こえた。私はその現実離れした老人の言葉を不思議と納得している。全く、奇妙な事だ、と自分でも思っていた。 「さぁ、どうじゃ?この決断はお譲ちゃんが決める。ただ、まだ決めかねているのなら今日で無くていい。私は、またここに来るからの」 老人は言う。私は、決断するまで時間はかからなかった。どうせ死ぬつもりで来たのだから、当然か。 「はい」 と、淡々と言う私に、老人は「ほう」と驚いたように言った。 「本当に後悔はしておらんのか?お譲ちゃんはまだ若い、それに純粋だ。まだ、楽しいことがあるかもしれんぞ?」 老人は私を説得してくれた。―随分と優しい死神だな、と私は思う。だが、私の決意は固くここで考え直すはずが無かった。 「はい」 と、私は再び強く頷く。 すると老人は目を瞑り、先程とは全く違う、低い声で言った。 「それでは、仕方ない。お譲ちゃん、そこの端っこに立って目を瞑ってくれないじゃろうか」 私は老人が指差した場所―それは偶然にも私が昨日下を見下ろしていた場所だった。私は大人しくそこへ立ち目を瞑った。すると老人がゆっくりと私の後ろに立った。足音は全く聞こえなかった。 「それじゃあ、これから始めるぞ。心の準備は良いじゃろうか?」 その老人の言葉に、私は頷いた。そして、その瞬間、私は意識を失った。 6. 私がふと気づくと、周囲は一面の青空だった。そして真下には見慣れた町。私は一瞬、混乱した。 だが、これがあの老人がしてくれた事だと気づくと私はスグに楽になった。 ―ああ、私が空を飛んでいる。本当に、夢のようだ。 気分の良くなった私は、空への散歩―いや、飛行を楽しむことにした。 町を見下ろしながら私は旋回、上昇、加速等をして自由に飛び回った。まるで、アニメの世界に来たような夢の光景。私は夢が叶ったという素晴らしさを全身で感じた。 果てしない蒼穹を飛び回る快楽は、今まで味わったことの無い最高の感覚だった。恐らく、人生の中で最初で最後の快楽だろう。 ・・何時間飛んだだろう。いつしか空は茜色に変わり、町の表情を様変わりさせていたいた。不思議な事に、空から見たその夕日は、なんだかとても綺麗で、私が大嫌いな黄昏時の景色も好きになれそうな気がした。 「どうだい、お譲ちゃん、満足したかい?」 気が付くと、老人が私の隣に居た。やはり私と同じように浮いている。 「はい、最後にこんな素敵な事をしてくださって、ありがとうございました」 何時に無く、素直な気がした。 老人は、その私の言葉を聞いて嬉しかったのか、嬉しそうに笑う。 「いえいえ、ワシはお譲ちゃんの笑い顔が見れただけでも嬉しいよ。生前では笑い顔なんて考えられなかったんじゃけどな」 私は、老人の言葉にハッとした。確かに私は笑っていた。今まで、作り笑いすら浮かべない私が、本当に笑っていた。 驚いてる私の姿を見た老人が、また優しい笑みを浮かべる。 「驚くことは無いんじゃよ。笑うということは人間として、ごく当たり前の感情じゃからな。ただ、君の場合はあまりに純粋すぎて、笑うのを忘れていたのじゃよ」 老人の言葉は、私にとって、理解できたのか出来なかったのか、良くわからなかった。ただ、死ぬ前に、何かとても言い事を聞いたような気がするのは間違いない気がした。 「―さて、お譲ちゃん。そろそろお別れじゃ。」 老人がふと、懐かしんだように言った。私はなんだか急に名残惜しくなるのが、自分でも感じられた。 「お爺さん。」 「ん?何じゃ?」 「―また、会えますか?」 それは、短いやりとりだったが、私の心の心配を、良く表していた会話だったと思う。 お爺さんは、そんな私の心境を察してくれたのか、これまた優しい笑みで 「勿論じゃ」 と、短く言ってくれた。とても短い一言だったけど、私はその一言で一気に安堵した。その時の私の顔は、とても穏やかな笑顔だったと思う。 「・・お譲ちゃん。時間のようじゃ。最後に、この世界をしっかりと見ておくんじゃぞ」 今度は、少し寂しげな表情を浮かべていった。私は老人が言ったとおりに、私が生まれ育った世界を見た。 赤い夕日、寂しげな町の明かり、見慣れた町、一面に広がる黄昏時の空― それらは、全てありふれたものだったが、今の私にとってはとても掛け替えのないものに思えた。 徐々に、私は目の前が暗くなってくる感覚になってきた。私は、目の前が真っ暗になる前に、何度も何度も、この世界の景色を目に焼き付けた。 ―そして、私は最後に、大嫌いだった夕焼けと、柔和な笑みを浮かべた老人を見て目の前が真っ暗になった。 翌日― 町外れの廃ビルの下で、高校生の少女の死体が発見された。 飛び降り自殺と見られているが、不思議な事に体の損傷が一切無かったと言う。 だが、それ以上に警察を奇妙に思わせたのが、その死んだ少女の顔が、とても穏やかで満足そうな笑みを浮かべていたことだった。 ―そう、その表情はまるで、夢が叶ったかのような幸せそうな表情だったという。 |